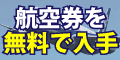クリストフォリの発明とピアノ
1709年、イタリア人であるバルトメオ・クリストフォリと言う名前の楽器製作者がいました。
彼は、打弦機構を持つ新しい楽器を発明し、打弦機構を持っていることによって、クラヴィコードとチェンバロの2つの長所をあわせもつ当時では、画期的な発明を成し遂げました。
ちなみに2つの長所とは、クラヴィコードの音の強弱が出せるところと、チェンバロの音の大きさのことです。
この発明品には、『ピアノ・エ・フォルテ・クラヴィ・チェンバロ』と呼ばれる、つまりは強弱の出せるクラヴィ・チェンバロが略されて現在のピアノと言う呼び方が生まれたと言われています。
ただ、当時はまだチェンバロの全盛期であったため、ピアノを使った作曲家は歴史には残っていないようです。
原因としては、当時のピアノ自体が作曲家の要求に応えるほどの演奏レベルを持っていなかったためと考えられます。
彼の発明したピアノの特徴として、まずハンマーの部分がフェルトではなく、羊皮紙を何層にも重ねられた表面に皮を貼ったものであったこと。
アクションの伝達率が現在のピアノが1:6であったのに対し、1:8であったこと。
チェンバロと同様に鍵盤のあがきが、現在では10mmなのに対して6mmであったことが挙げられます。
他にも、クリストフォリは1726年に、エスケープメントやダンパーを発明しました。
それらをクリストフォリの弟子である"ジルベルマン"が改良して、ハンマーフリューゲルと呼ばれるものを製作します。
1736年にJ.S.バッハにこのピアノを紹介し、1747年には、バッハがフレデリック大王にこのピアノを使ってピアノを演奏したと言う記録が残っているそうです。
彼は、打弦機構を持つ新しい楽器を発明し、打弦機構を持っていることによって、クラヴィコードとチェンバロの2つの長所をあわせもつ当時では、画期的な発明を成し遂げました。
ちなみに2つの長所とは、クラヴィコードの音の強弱が出せるところと、チェンバロの音の大きさのことです。
この発明品には、『ピアノ・エ・フォルテ・クラヴィ・チェンバロ』と呼ばれる、つまりは強弱の出せるクラヴィ・チェンバロが略されて現在のピアノと言う呼び方が生まれたと言われています。
ただ、当時はまだチェンバロの全盛期であったため、ピアノを使った作曲家は歴史には残っていないようです。
原因としては、当時のピアノ自体が作曲家の要求に応えるほどの演奏レベルを持っていなかったためと考えられます。
彼の発明したピアノの特徴として、まずハンマーの部分がフェルトではなく、羊皮紙を何層にも重ねられた表面に皮を貼ったものであったこと。
アクションの伝達率が現在のピアノが1:6であったのに対し、1:8であったこと。
チェンバロと同様に鍵盤のあがきが、現在では10mmなのに対して6mmであったことが挙げられます。
他にも、クリストフォリは1726年に、エスケープメントやダンパーを発明しました。
それらをクリストフォリの弟子である"ジルベルマン"が改良して、ハンマーフリューゲルと呼ばれるものを製作します。
1736年にJ.S.バッハにこのピアノを紹介し、1747年には、バッハがフレデリック大王にこのピアノを使ってピアノを演奏したと言う記録が残っているそうです。
クリストフォリの発明とピアノ関連エントリー
- アップライトピアノとグランドピアノ
- ピアノの音
- ショパン
- ブラームスの個性
- ブラームス
- ソナチネ
- ショパンのピアノ練習曲2
- ショパンのピアノ練習曲1
- 上級者向けピアノ練習曲
- ピアノ練習曲3
- ピアノ練習曲2
- ピアノ練習曲1
- ピアノのグレード
- ピアノ調律師になるためには
- ピアノ調律師の状況
- ピアノ調律師
- ピアノに飲み物をこぼしたら
- ピアノカバー
- ピアノのコンディションをたもつ
- ピアノの調律の必要性
- カワイの歴史とピアノ
- ヤマハの歴史とピアノ
- ピアノの普及とスタンウェイ一族
- ピアノの進化
- エラールのレペティションレバー
- 産業革命とフランス革命のピアノに与えた影響
- ペダル・アップライトピアノの発明とエラール
- スタインの発明とピアノ
- クリストフォリの発明とピアノ
- ピアノが生まれる前