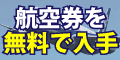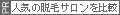ピアノエントリー一覧
- アップライトピアノとグランドピアノ
- ピアノと言えば、本来はグランドピアノを指します。しかし、学校や幼稚園などの、あまり広いスペースをピアノにとることができないところでは、アップライトピアノが置かれることが多いようです。ですが、やはりグランドピアノは、豊かな響きや、多彩な音色、弾くときのタッチや、幅広いダイナミックレンジなど、すべてにおいて表現力が豊かです。過去の偉大な作曲家たちの作り上げたピアノ曲を弾きこなすにはやはり、グランドピアノのほうが迫力も出るというものです。グランドピアノの特長としては、ピアニッシモからフォルテッシモまで...
- ピアノの音
- ピアノとは、音を楽しむいわば娯楽の道具でもあります。ピアノの音の楽しみかたは、自分で弾くということもありますが、弾いて音を聴くということでもありますよね。音を出すということは、まわりの住人にも聞こえるわけですから、それなりに暗黙のルールを守らなければなりません。それがピアノを楽しむためのエチケットというわけです。ご自宅のまわりに民家のない方なんて、そう滅多にいるものではありません。やはり、近所づきあいというものもありますし、近所の方々との円満な生活のためにも、この暗黙のルールはできる限り守ったほ...
- ショパン
- 偉大なピアニストとして有名なショパンのフルネームは、フレデリック・フランソワ・ショパン。ポーランドの音楽家として名高いショパンは、「ピアノの詩人」という異名を持ち作曲家としてもピアニストとしても有名でありましたショパンは、美しい旋律を生み出し、さまざまな形式を用い、半音階的和音などのピアノの表現様式を広げた。それまでのピアノになかった新しいピアノを生み出すことに貢献した偉大なピアニストの一人です。ショパンは、なかなか体の強いほうであるとは言えず、生涯を通して肺結核に悩まされた病弱な音楽家として知...
- ブラームスの個性
- ピアノの練習曲の作曲家としても有名な"ヨハネス=ブラームス"は、大くのロマン派の作曲家と同じように、ベートーヴェンを崇拝していた。彼の個性は、ベートーヴェンに近いものがあったという。自然を愛し、たびたび散歩にでかけては、たびたび子供たちに、キャンディをあげる。その反面、大人に対しては、無愛想にふるまうことが多かったという。自分の気持ちを素直に伝えることを苦手とし、自分の作品を語ることすらも嫌がるほどだったそうだ。しかしながら、ピアニストとして優れていたため、友人のサロンなどで、たびたび演奏を求め...
- ブラームス
- 19世紀のドイツの作曲家であり、ドイツ音楽における「三大B」の一人として知られている"ヨハネス=ブラームス"をご存知でしょうか。彼の作風は、ロマン派音楽の範疇にありますが、古典主義的な面も強いといわれています。ブラームスがベートーヴェンの後継者であると信じている人はたくさんおり、指揮者であるハンス・フォン・ビューローは、彼の交響曲第1番を「ベートーヴェンの交響曲第10番」と呼び、今もそのタイトルが広く使われているほどです。ブラームスは、1833年に生まれ、1897年に没する64年を生きました。ハ...
- ソナチネ
- ソナチネとは、クラシック音楽のジャンル名のことを言い、ソナティナなどとも言われます。バロック音楽においての、ただの短い器楽曲のことをいい、カンタータの器楽合奏の導入曲や間奏のことを漠然とあらわすのに使われていました。古典派音楽以降には、わかりやすくて演奏しやすい、短いソナタのことをいうようになりました。たいていのソナチネでは、第1楽章は、ソナタ形式で作曲されますが、展開部が短く作曲されているか、展開部自体が存在しないことがあります。楽章数としては、だいたい2章か、もしくは3章程度であることが多い...
- ショパンのピアノ練習曲2
- ピアノの詩人として名高い、ポーランド生まれのピアニストである「フレデリック・ショパン」という人物がいました。彼の作曲した多くのピアノ練習曲は、多くの人たちに愛され、中にはタイトルまでついたものもあります。3つの曲集からなる彼のピアノ練習曲は全部で27曲あります。ここでは、12の練習曲 Op.25について、簡単に説明させていただきたいと思います。まず、この曲集が作曲された年代は1832年~1836年といわれていて、出版されたのは、1837年ごろだそうです。曲目は、順に、第1番 変イ長調 『エオリア...
- ショパンのピアノ練習曲1
- ポーランドに生まれた、「ピアノの詩人」としても名高い"フレデリック・ショパン"をご存知でしょうか。彼の作曲したピアノの練習曲は、全部で27曲あります。これらの曲は、演奏会などで取り扱われることも多く、中には練習曲にもかかわらず、タイトルのようなものがついて親しまれているものもあります。12の練習曲 Op.10と、12の練習曲 Op.25と、3つの新練習曲の3つの曲集からなる彼の練習曲は高度なものが多く、なかなか初心者には練習曲として弾くことを許しません。ここでは、12の練習曲 Op.10について...
- 上級者向けピアノ練習曲
- ここでは、初心者の方には難しいと思われる、上級者の方向けのピアノ練習曲を簡単に、ご紹介いたします。ピアノが上達したからといって、気を抜いてはいけません。ピアノはさぼっているとすぐに弾けなくなります。個人差があるとはいえ、ピアノというものは、弾きこめば弾きこむほどに上達していくものです。ある程度ピアノが上達して、だいたいの曲は少し練習するだけで弾くことが出来るようになってしまうと、だんだんそれに慣れてしまいます。そうするとなかなか難しい曲に挑戦しようという気持ちにならず、自分と同じレベルの曲ばかり...
- ピアノ練習曲3
- みなさんは、普段の練習曲には何をお使いですか??なかにはピアノを独学ではじめてみたいけれど、何の練習曲から取り組めばいいのかよくわからない・・・。今自分が練習している曲は、どれくらいのレベルなんだろうか。などなど、心に浮かんでくる疑問はさまざまであろうと思いますが、ここでは簡単に、練習曲について解説したいと思います。まず、もっとも初歩的であり、ピアノを取り組み始めた方によく使われるのがツェルニーの100番です。ツェルニーには、先程申し上げました100番 Op.139 のほかに、110番 Op.4...
- ピアノ練習曲2
- ハノンやブラームスに代表される、いわば機械的な練習曲とは異なった、上級者向けの練習曲というものがあります。みなさんもピアノを練習していけば、いつかは初心者ではなくなり、上級者のレベルに到達するわけです。初心者のかたに練習が必要なように、上級者となっても練習は必要なのです。というか、ピアノには終わりがありませんので、どこまでも高みを目指していけるのですが・・・。昔の著名な演奏家たちもはじめは初心者であり、しだいに上級者になり、これらの上級者向けの練習曲ができあがったわけです。それに代表されるものが...
- ピアノ練習曲1
- みなさんは、ピアノの練習をするとき、どのような曲を弾いて練習していらっしゃいますか??ピアノの教室に通っている方も、独学で習っている方も、先生や書籍などから個人個人のレベルにあった練習曲を課題として習っていることと思われます。ほとんどの練習曲といったものには、曲ごとに修得するべき演奏技術が含まれており、その技術を曲の中で繰り返し弾くなどすることで、その演奏技術をマスターするという形になっているようです。そして、このような練習曲は、教育的な練習曲のため、単調なリズムや、同じような音をただただ繰り返...
- ピアノのグレード
- ピアノには、国家試験などの定められた資格や試験などはまだハッキリありませんが、やはり、ピアノを学んでいるうちに、自分が今どれくらいのレベルであるのか気になるときは多々あると思われます。そんなとき、多くの人たちが受けるのがグレードです。有名なヤマハのグレードとカワイのグレードがありますが、ここではヤマハのグレードについて少しお話しすることにいたします。ヤマハのグレードは、1級から13級まであります。さらに細かく分類がされており、13級から11級が鍵盤初期学習者用で、10級から6級はピアノ学習者のた...
- ピアノ調律師になるためには
- ピアノの調律師となるためには、何が必要で、どうしたらいいのでしょうか。一般的に、ピアノの調律師になるためには、全国にある20ヶ所ほどのピアノ調律師養成学校に通って訓練をしていくようです。ほかにも、大手の楽器メーカーなどのなかには、会社内に養成所を設けるなどして、自社で働く調律師を養成しているところもあります。そして、最近増加傾向にあるのが、音楽療法などのコースと併せて、調律科を設けている専門学校などがあります。調律のプロとして活躍するためには、とにかく経験が大切です。そのためにも、とにかくたくさ...
- ピアノ調律師の状況
- 今現在のピアノの調律師の状況ですが、全国で毎年、だいたい100人ほどのピアノの調律師が生まれています。それに対し、現在の家庭のピアノは、販売台数も減っており、飽和状態にあります。調律の必要性のない電子ピアノが普及していっていることも背景に、ピアノの需要は現在下降気味であると言えます。そんな状態の中で、楽器販売店の中には、調律師にピアノの販売数のノルマを要求するところがあったりと、決して簡単な仕事ではないのです。こう言ってしまうと、ピアノの調律師なんてならないほうがいいのかなぁと感じてしまうかもし...
- ピアノ調律師
- ピアノの調律師とは、ピアノをより長く、より良い状態に保つためにお手入れをしてくれる存在です。彼ら調律師なくして、ピアノをより良く、長く保っていくことはなかなか難しい・・・とは言いすぎではないと思っています。彼ら調律師は、ピアノの88鍵を自由自在に操るテクニシャンです。今の日本でピアノを所有している家庭は、およそ5分の1だと言われています。ということは、5軒に1軒はピアノを所有しているという計算になりますよね。最近では、ピアノの売れ行きは減少傾向にありますが、それでも、昔から家庭などにあるピアノを...
- ピアノに飲み物をこぼしたら
- あまりないとは思われますが、飲み物を飲みながらピアノを弾いたりするとき・・・うっかりピアノに飲み物をこぼしてしまったことってあるでしょうか。人間生きていれば何が起こるかわからないものです。「そんなことあるわけがない」と思っていても、何かの拍子に、不注意で、ピアノに飲み物をかけてしまうかもしれません。それが、ジュースであろうと、コーヒーであろうと、紅茶であろうと水分(水気のあるものや、液体など)がピアノの中に入っていってしまうのは少々ゆゆしき問題です。なぜなら、ピアノを形成している部品には、木でで...
- ピアノカバー
- ほとんどのみなさんは、昔、幼稚園や保育園、学校などで見かけたことがあるだろうと思いますが、よくそういった施設などにあるピアノには、ピアノ本体をそっくりと包み込んでいるマントのような黒い大きなカバーがかかっていたりしますよね??あの大きなカバーって、ピアノにとっては本当に必要なのでしょうか。学校や幼稚園では必要不可欠なものであるということで使い続けられていました。しかし長期的に見ると内部保護の観点から逆効果になってしまうことがあるのです。たとえば、一般家庭でこのカバーをピアノにかけたまま4~5年ほ...
- ピアノのコンディションをたもつ
- ピアノのコンディションをたもつために何が必要だと思われますか??ピアノにとって大敵なのは、湿気ということもあり、袋に入れられた防湿剤はたくさん使われています。ただし、ピアノというものは密閉された箱ではありません。外の空気といつも接しているわけですから、恒常的湿気の多いところなどでは、どんなに湿気を吸い込んだところでいつかは限界がきてしまうでしょう。そういった方法も悪くはありませんが、それよりも有効なのは部屋の中に除湿器を置くことです。除湿器を部屋の中に置くことで、湿度の調整をしたほうがはるかに効...
- ピアノの調律の必要性
- 人間が定期的に病院に行ったりして、悪いところを見つけて治さなければならないのと同じようにピアノにもそういうことが必要なのです。人間は病院などで定期健診を受けますが、ピアノには調律師さんたちの手によって「調律」ということをしてあげなければなりません。なぜなら、私たちの使っているピアノの中には、木材や羊の毛などの天然のものから作られている非常に精密な部品がたくさん使われているからです。それらは、天然のものから作られているため、日々の気温の変化や湿度などにとても敏感です。人間も、毎日の変化の中で生きて...
- カワイの歴史とピアノ
- 現在のカワイ(河合楽器製作所)は、創業者である「河合小市」という人物が、日本楽器製作所を退職したのちに"河合楽器研究所"を設立したことが始まりです。河合小市氏が退職したあと、天才として有名だったという河合小市氏を慕って、日本楽器製作所で働いていた技術者たちも小市氏に続いて次々に退職していきました。主な退職者としては、平出幸太郎氏、県松太郎氏、伊藤勝太郎氏、斉藤哲一氏、森健氏、杉本義次氏、青木金吉氏などが挙げられます。彼らは、1928年にグランドピアノの製造を始めました。その翌年である1929年に...
- ヤマハの歴史とピアノ
- 日本の有名なピアノメーカーとしてヤマハがあります。ピアノを学んでいる人のほとんどがこの名前をどこかしらで聞いたことがあると思います。明治21年、西暦でいうと1887年です。このころ静岡県の浜松市で暮らしていた、宮大工の山葉寅楠(やまは とらくす)という名前の人物がいました。彼は、浜松小学校で使っていた足踏みオルガンの修理を頼まれ、見事修理したことからオルガン作りを開始したのです。そして、その後の明治33年に記念すべき第一号の国産のアップライトピアノである「ヤマハカメンモデル」を完成させました。ま...
- ピアノの普及とスタンウェイ一族
- 産業革命によってピアノには大きな変化がもたらされました。それは、アメリカでの大量生産による低価格化の進行とアップライトピアノの市民層への普及の拡大といった変化です。このころでは低価格で良質なアップライトピアノがキンボールや、ボールドウィンなどによって大量に作られていたそうです。その後、第二次世界大戦が勃発します。この戦争の結果、ヨーロッパは荒れ果ててしまい、ドイツなどのピアノメーカーは生産を休止せざるを得なくなりました。しかし、戦勝国であったアメリカにいたスタンウェイは戦後も生産を休止することも...
- ピアノの進化
- 1825年に、アメリカでボイラー工場を経営していた経営者のアルフェーズ・バブコックは本格的な鋳鉄製のフレームを作りました。当時のピアノの音域は演奏者の要求があり、4オクターブであったものが次第に5オクターブに増え、6オクターブへと増えていき、木製の支柱のみでは鉄線や真鍮線であってもその張力を支えきれなくなっていたのです。その結果、鉄骨でブロードウッドが補強し、バブコックが鋳鉄製フレームを考案するところにいたったのです。そして1819に、ダイアモンドダイスが発明されて、1835年には精度の高くなっ...
- エラールのレペティションレバー
- フランスに生まれた、ピエール・エラールという名前の人物がいます。彼は1809年に、フランス革命の前にイギリスに渡り、当時のピアノにたくさんの改良を加えていった人物です。そしてその彼の発明の中でも、最高の発明であると言われているのが「レペティションレバー」の発明です。これは、鍵盤の動作をハンマーという部分に伝えるジャックをすばやく始動位置に復帰させることにより、いままでよりも早く連続打鍵をすることができるようにするものです。そしてその後の1821年には、これにさらに改良を加えてダブルレペティション...
- 産業革命とフランス革命のピアノに与えた影響
- バロック期ころにピアノが発明されてからさまざまな楽器製作者が少しずつ改良していったのがピアノの歴史です。ピアノは、さまざまな生活背景のもとに少しずつ今のピアノに近づいておりました。ここにきて、ピアノは急速に現代のピアノにぐんと近づきます。18世紀後半に起こった産業革命により、ブルジョアといわれる富裕層の市民階級が生まれました。そして彼らは、貴族社会の象徴でもあるピアノを手に入れようとします。こうしてピアノの需要が急増してしまい、家内工業的な少量生産では、供給が追いつかなくなってしまいます。そのた...
- ペダル・アップライトピアノの発明とエラール
- 1783年には、イギリスのジョン・ブロードウッドと言われる楽器製作者がペダルを発明しました。ペダルは今ではピアノには欠かせないものですが、当時彼が発明するまでペダルは棚板下にあるレバーをひざで操作するタイプのダンパーだったなんて驚きですよね。しかし、さらに驚いたことに、1791年に亡くなったモーツァルトは、ペダルの存在を知っていてもペダルの付いたピアノでは作曲をしなかったそうです。ということは本来のモーツァルトの曲にはペダル記号はなかったということになります。ダンパーペダルの演奏に与える効果はと...
- スタインの発明とピアノ
- チェンバロ製作者であった、スタインと言う名前の楽器製作者が、1775年に独自のエスケープメント機構を兼ね備えたピアノの製作に取りかかりました。そして彼は、当時のピアノとしては、とても弾きやすい軽やかなタッチだったと言われているほどのピアノの製作に成功したのです。この頃では、ピアノのハンマーアクションの完成度も高くなってきており、たくさんの作曲家に受け入れはじめました。そして、1756年にオーストラリアで7年戦争が勃発したことをきっかけに、多くの楽器製作者が移住を開始しました。この7年戦争をきっか...
- クリストフォリの発明とピアノ
- 1709年、イタリア人であるバルトメオ・クリストフォリと言う名前の楽器製作者がいました。彼は、打弦機構を持つ新しい楽器を発明し、打弦機構を持っていることによって、クラヴィコードとチェンバロの2つの長所をあわせもつ当時では、画期的な発明を成し遂げました。ちなみに2つの長所とは、クラヴィコードの音の強弱が出せるところと、チェンバロの音の大きさのことです。この発明品には、『ピアノ・エ・フォルテ・クラヴィ・チェンバロ』と呼ばれる、つまりは強弱の出せるクラヴィ・チェンバロが略されて現在のピアノと言う呼び方...
- ピアノが生まれる前
- ピアノが誕生する前、クラヴィコードと、チェンバロと言うものがあったそうです。クラヴィコードは、紀元14世紀ごろの誕生であると言われています。ルネッサンス期に主流であったクラヴィコードの音域は、4オクターブ程度がほとんどで、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの愛用していたクラヴィコードは5オクターブあったそうです。クラヴィコードは、とても簡単な構造をしており、2つの駒の上に張られている弦をタンジェントと呼ばれる別の駒で突き上げて音を出していたため、音量がとても小さく、現在のピアノで言うとピアニッシモか...